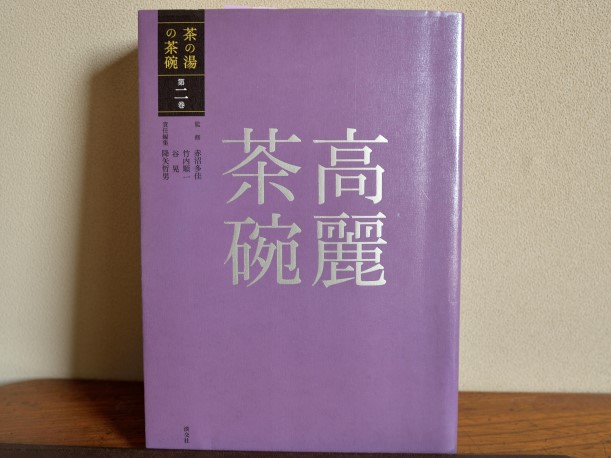高麗茶碗を学ぶ

解説--奥高麗茶碗を特集するために高麗茶碗について調べることになりました。その中で2023年2月に刊行された本「茶の湯の茶碗 第2巻 高麗茶碗」 降矢哲夫編集 淡交社がとても参考になり、かつ面白かったので紹介したいと思います。
高麗茶碗はもともと14世紀~16世紀に朝鮮半島南部の民陶で日常の器として焼かれていたもので、室町時代以降に日本に持ち込まれ、茶の湯の茶碗として見出されて伝世したものです。その背景には侘茶の流行があり、当時の茶人が茶碗として見立てるということがありました。日本では江戸時代中期(17世紀後半)以降、茶人らによって分類や名称が整理され、おおよそ現代のような名称が用いられるようになったと記載されています。私が好きな安土桃山時代、まさに利休、織田信長や豊臣秀吉らが茶会で使った茶碗でもあります。
高麗茶碗は多岐にわたっていてその特徴から詳細に分類されています。本書は名物と言われる茶碗をとりあげ、茶碗の詳細な写真、その特徴すなわち、姿、形、胎土、釉掛け、釉薬の調子、技法、高台や見込みの部分の説明があって興味がつきません。
そして、茶碗の銘の由来や、所持していた人(武将)とその時代背景を知ることでより楽しめる内容になっています。
各々の茶碗に歴史と物語があって、まるで短編の時代小説を読んだいるかのような気分になります。
いくつか例を挙げたいと思います。
●大井戸茶碗 銘 筒井筒 (Tutuitutu)
姿、形が私の好みであり、銘の由来が面白い。
『豊臣秀吉が愛蔵した茶碗であり、もともと南都(奈良)の東大寺近くの水門に住んでいた茶人善玄が所持しており、それを筒井順慶が譲り受けて所持していたことから筒井の井戸茶碗と呼ばれた。その後、順慶より秀吉に献上された。ある茶会でこの茶碗を近習が誤って割ったことで秀吉の機嫌を損ねたが、その場に居合わせた細川三斎が伊勢物語の一節に因んで狂歌「つつ井筒いつつにかけて井戸ちゃわん とがをば我におひにけらしな」と即興、その場を取り繕った出来事から「筒井筒」の銘がつけられたとされる。
天正15年(1587)の北野大茶湯の際に新田肩衝とともに使われた井戸茶碗が本碗と言われている。また、天正18年9月13日には、千利休が秀吉を迎えた茶会で「つついのいと茶碗」を2畳敷の茶室で用いた記述がある。その後、京都山科の毘沙門堂へと伝わっている。』
●狂言袴茶碗 銘 藤袴 (FujiBakama)
『狂言袴とは、筒型で茶碗の外周に白黒象嵌で鶴や花、雲などが施された茶碗のことで、その文様が狂言師の袴の紋に似ていることからつけられた名称とされている。織田信長の弟で、千利休に茶を学んだ織田有楽が所持していた茶碗である。
藤袴は山上憶良が万葉集のなかで選んだ、秋の七草の一つで、その名は藤色をした花の色と花弁が袴のような形をしていることに由来するとされる。この種の茶碗は、天正18年(1590)12月8日昼の石田三成の茶会で用いられた記録があることや、千利休も同形の茶碗を所持しており、桃山時代によく用いられていたことがわかる。』
そこで、10月中旬に21世紀の森と広場へフジバカマを観察しにいきました。小さな花の集合で派手さはなく楚々とした雰囲気です。目を凝らして見ると、小さな花から長く白い花弁が2本づつ出ていて、たぶん古人はこの姿を袴として捉えたのですね。古くから日本人に愛されてきたキク科の植物との説明があります。
●無地刷毛目茶碗 銘 千鳥
姿は私の好みではありませんが、伊達家の由緒正しい茶碗です。
『この茶碗は、戦国武将で茶人としても名高い伊達政宗が所持していた。寛文5年(1628)3月12日には徳川将軍2代・秀忠が、同月26日には徳川3代・家光がそれぞれ仙台藩江戸屋敷への御成(Onari)をおこなった際に、千利休が所持していたとされる青磁砧花入れとともに用いられている。また、仙台藩4代藩主・伊達綱村も茶の湯に造詣が深く、元禄6年(1693)11月18日から元禄16年7月5日までの間に江戸屋敷や仙台城において、15回にわたりこの茶碗を用いた茶会を開いている。箱蓋表には「千鳥」と墨書された張り紙があり、伊達家の宝物類を記した「観閣宝物目録」によると、仙台藩2代藩主・伊達忠宗が記したものとされる。』
本書の全編にわたって、このような話がちりばめられていてなかなか楽しめます。
次に茶碗の分類について気になったことを述べたいと思います。
◎伊羅保茶碗 (Irabo)について
肌に小さないぼのような突起があることや、胎土に含まれる粒子が”いらいら"とした質感であることからこの名がついたとされるが、詳細はわからないと記載されています。
たしかに鉄分が多く石や砂が混じる胎土で見た目は汚い。この自然な汚らしさが良いのだろうか? 草案の茶室で使われる侘茶にはぴったりと思いますが、個人的には好きになれません。
掲載されている伊羅保茶碗には、口縁のふちに土切れによる段差(べべらというらしい)が生じたものがいくつかあります。現代の常識ではこういったものは失敗作としてろくろ成形後にその場でつぶして焼かないのが普通です。当時、日本からの注文によって造った朝鮮の陶工はこれを良しとしたのだろうか。
◎井戸茶碗について
井戸茶碗が用いられるようになる天正年間(1573~1592)は、利休によって簡素で小さな草庵の茶室が成立していく時期に重なることから、大振りの茶碗ではなく、小井戸茶碗や青井戸茶碗といった小ぶりものがおもに使われたようです。我々は井戸茶碗というと豪快な大井戸を想像しますが、侘茶には小ぶりのものが適していたということです。なお、小井戸を古井戸と表記することもあります。
◎熊川茶碗 (Komogai)について
解説 奥高麗茶碗でも述べましたが、奥高麗茶碗は熊川茶碗を手本にしたと言われています。たしかに、熊川茶碗はおおらかでいいですね。
熊川は、朝鮮半島の南、釜山に近い現在の慶尚南道昌原市にあった港で、この周辺で焼かれたやきものがこの港に集められ積み出されたことに因んでの名称と思われるとあります。掲載されている熊川茶碗の中で、特に真熊川茶碗 銘 千歳(Chitose)がお気に入りです。唐津茶碗の原型のような姿です。銘の千歳は、鎌倉時代の思想家で歌人の慈円の和歌
「雲の上に齢(yowai)ゆずると鳴鳥(nakutori)は 君が千歳を空に知れとや」(拾玉集第3巻3767番)からとったものです。五島美術館が所蔵しています。
本書の詳細な写真と丁寧な説明によって高麗茶碗について学ぶことができ、より身近かに感じられるようになりました。私にとって、やきものと歴史を学べる貴重な本です。今後、高麗茶碗が出品されている展覧会に行くのが楽しみです。