母の疎開先 秩父小鹿野町
2023年10月投稿
母への手紙
昨年、88歳になる私の母はコロナ下で亡くなりました。その後実家で母の遺品を整理していたら、昭和20年に母が学童疎開していた埼玉県小鹿野村の寺院での集合写真がでてきました。母は生前、小鹿野村の寺に疎開していたことを懐かしく話すことがありました。また、私が学生のときに両神山の登山で小鹿野町を通ったことがあって、母にその話をしたら小鹿野町へ行きたがっていたのを思い出しました。この写真を持って小鹿野町の母の疎開先に行くことを思い立ちましたが、なかなか疎開先の寺を特定できませんでした。
ところが、奇跡とでも言いましょうか。米寿を迎えた中央区月島第二中学校出身者の同期会の案内が実家に届いたのです。同期会の幹事の方に頼んで出席者に聞いてもらい、母が在籍していた月島第二国民学校の生徒は小鹿野町の「鳳林寺」、「十輪寺」、「正永寺」と坂本屋旅館に分かれて疎開したこととがわかりました。
こうして小鹿野町の寺院を訪ね、かつて登山をした両神山の麓の温泉に泊まることにしました。


小鹿野町探訪 鳳林寺
7月中旬早朝に自宅を出発して車で小鹿野町に向かいました。
先ず、小鹿野町を東西に走る国道299号沿いにある鳳林寺に向かいました。山門が古びていて良い雰囲気です。本堂はかなり立派な建物です。母の疎開先の写真を見ながら共通点を捜しましたが、どうもここではないようです。
せっかく来たので御朱印をお願いし、住職の奥様と思われる人(年齢は80歳とのこと)に母の写真を見せてここに来た事情を説明しました。彼女は写真の場所は十輪寺だろうと言いました。その写真に写っていた十輪寺の住職に見覚えがあったのです。現在の十輪寺の住職は孫の代になっていることも教えてくれました。昭和20年、現在80歳の彼女は未だ赤ん坊で、鳳林寺に学童疎開していた子供達に抱っこされ可愛がられたそうです。しかし、疎開していた子供の母親たちが赤ん坊のダニやノミがうつるといって反対したそうです。また、学童疎開に同伴した先生に和歌を詠む人がいて、この寺で赤ん坊を抱いた思い出を和歌に詠み、後年自作の歌集を送ってくれたと言っていました。
最近まで、学童疎開した多くの人がちょくちょく鳳林寺を訪ねてきたと聞いて、あんなに懐かしく小鹿野の話をしていた母を何故この地に連れてこなかったのかと後悔しました。

鳳林寺の山門

鳳林寺の立派な本堂
小鹿野町 十輪寺
小鹿野町中にある十輪寺を訪ねました。住職と奥さんに御朱印をいただき、ここに来た事情を話しました。現在の住職(50歳くらい)は 母の写真に写っている住職の孫にあたりますが、本人が「自分が丸眼鏡をかければこの写真にそっくりだ」と言ってみんなで笑ってしまいました。確かにそうなのです。学童疎開先での写真の背景の松が現在も残っていて、撮影場所を特定できました。住職は「この写真に写っている梅の木がそこの木です」と説明してくれました。母が疎開していた寺はまさにここだったのです。住持と奥さんはとても親身になってくれて、私達がここに来たことを喜んでくれました。私達はとても暖かな気持ちになりました。母は満足してくれたでしょうか。
境内の写真を沢山撮ったのですが、芭蕉の句碑があることを帰宅してから知りとても残念に思いました。
十輪寺の資料には、小鹿野の俳人 中阿坊が芭蕉の100年忌に建てたとあります。
寛政5年(1793)十月十二日
「梅が香に のつと日の出る 山路かな」 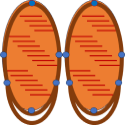




十輪寺の松
樹齢約200年と言われる現在の松。松は鶴が羽を広げたような形をしている(写真1)。この松を背景に学童疎開の写真が撮られた。
写真3は本堂から見た小鹿野の山並み。




十輪寺の本堂
本堂の入り口天井には絵が描かれている。本堂の右側の建屋は改築されていた。そこで御朱印をいただいた。
写真3枚目は十輪寺と鳳林寺(右側)の御朱印。
小鹿野町 正永寺、わらじかつ丼
十輪寺は町中にあるせいか、やぶ蚊がおおくて私は6か所も刺されました。すぐドラッグストアーに駆け込んでムヒをつけてから十輪寺からほど近い正永寺に向かいました。ここでは御朱印はやっていないと言われ、住職と話をする機会はありませんでした。
朝は曇天だったのですが、正永寺に着いた頃から青空がでてきて暑さ、日差しが厳しくなりました。正永寺の山門と本堂はやや高台にあって山門を吹き抜ける風が心地よく、妻と二人でしばらく山門で涼んでいました。山の端に両神山の岩稜が見え隠れしました。
このとき檀家で八王子から墓参りに来た人と話をしたのですが、自分の代で墓を見る人がいなくなってしまうので、そろそろ墓じまいを考えていて住職と話をしてきたところだと言っていました。山門脇に咲く桔梗がとても鮮やかでした。
昼食は町中の十輪寺近くにある「えびすや」という食事処で名物の「わらじかつ丼」を食べました。大きなわらじ形のかつが2枚のっているとのことでさすがに食べきれないと思い、ミニサイズのものを頼みました。かつに滲みこんだたれが美味しく、硬めのご飯とのマッチングが絶妙でした。うな重の秘伝のたれに似ていると思います。そういえば、十輪寺の門の天井に大わらじがあったのですがいわれがあるのでしょう。



正永寺の山門
山門は高台にあって風が通る。
写真2は境内の桔梗。
ボルダリングと両神荘
昼食後、宿泊先の温泉旅館 両神荘に向かいました。
そして両神荘の近くにあるクライミングパーク神怡舘でボルダリングをしました。インドアの人工壁で傾斜が80°、90、110°~といった壁があり、15人ほどが楽しんでいました。私は実に30年ぶりのクライミングで、人工壁のボルダリングは初めての経験です。施設のスタッフからルールや注意事項を聞いてからやさしい壁から少しづつ難しいルート(課題)に挑みました。落ちてケガをしたくないので、できるだけ安全かつ慎重に登りました。どうしても登れない課題があって4回ほどトライしたのですがあと一歩の勇気がでなかったようです。
両神荘では温泉と日本酒を満喫しました。秩父の地酒「秩父錦」が気に入ってお土産で購入しました。私は日本酒というとほとんど辛口を飲みますが、今回はやや甘口のこの酒を選びました。
夜、両神荘の脇を流れる小森川でホタル見学があるというので楽しみにしていたのですが、ボルダリングの疲れとほろ酔いで動けなくなり行けませんでした。



神怡舘と両神荘
ボルダリングを楽しめる神怡舘。背後の山が両神山に至る。
山麓の落ち着いた場所にある両神荘(写真2)。



