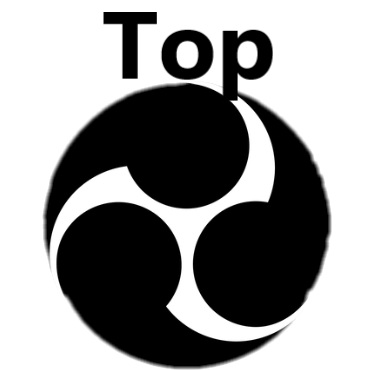会津と蒲生氏
2024年6月投稿
向羽黒山城から蒲生秀行廟へ
今回は蘆名盛氏が築いた山城 向羽黒山城跡から蒲生秀行廟を巡りました。
5月の飯豊連峰の写真を撮ろうと思い、向羽黒山城の本丸跡の岩崎山山頂に行きました。陽だまりの山頂にはツツジが咲き始めていました。今年は例年に比べて4月の気温が高かったせいか、飯豊連峰の残雪は少なくやや迫力が欠けます。
さて、山頂から磐梯山方面を見ると阿賀川を隔てて門田の町並みが見えます。会津若松市街の南にあたります。ここに蒲生秀行の墓があります。秀行は戦国武将 蒲生氏郷の嫡子です。
また、本ページの後半では伊達政宗から蒲生秀行までの歴史をまとめました。
向羽黒山城の本丸跡(岩崎山山頂)



山頂のツツジ
5月初旬、あちらこちらにツツジが咲いていました。
山頂には背の高い松の木がニョキニョキ植わっています(写真2)。




飯豊連峰と磐梯山
写真1,2は 会津本郷の町並みそして会津盆地の向こうに飯豊連峰を望みます。
写真3は 磐梯山の方角で阿賀川のむこうの町が門田です。
蒲生秀行廟と館薬師堂
住宅地の中に明るく清々しい公園があって、その端の一画に立派な墓陵がありますます。藁ぶき屋根の廟には鉄製の支柱で支えれた屋根がついていて雨が降っても濡れることが無いように保護されています。
閉じた扉から中を覗くと目の前に大きな石造りの五輪塔(2.7m)があってびっくりしました。
「この廟屋の建立は秀行没年の1612年頃と考えられる。」と説明があります。
また、公園内には館薬師堂があります。このお堂も蒲生家が関わっています。説明によれば、
「秀行の跡を継いだ忠郷は幼少(2歳)の頃 病弱でしたが北山薬師堂で護摩祈祷を行い、その御利益によって成長できたことから引真院の境内に瑠璃光薬師堂を造営し後に館薬師堂と呼ばれるようになった。現在も行われている"二つ児参り"は上記伝承に因むもので2歳児の無病息災が祈願される。現在のこの建物は引真院の主要御堂であったと思われる。」とあります。若松三十三観音第27番札所
館の花 盛りの祈りはよもの山 静かに雲も空に棚引く
まさに本歌にぴったりの場所でした。 



蒲生秀行廟
廟の左には会津磐梯山が見える(写真2)。

館薬師堂
薬師公園内には遊具やゲートボール場があって子供連れが遊びに来ていました。